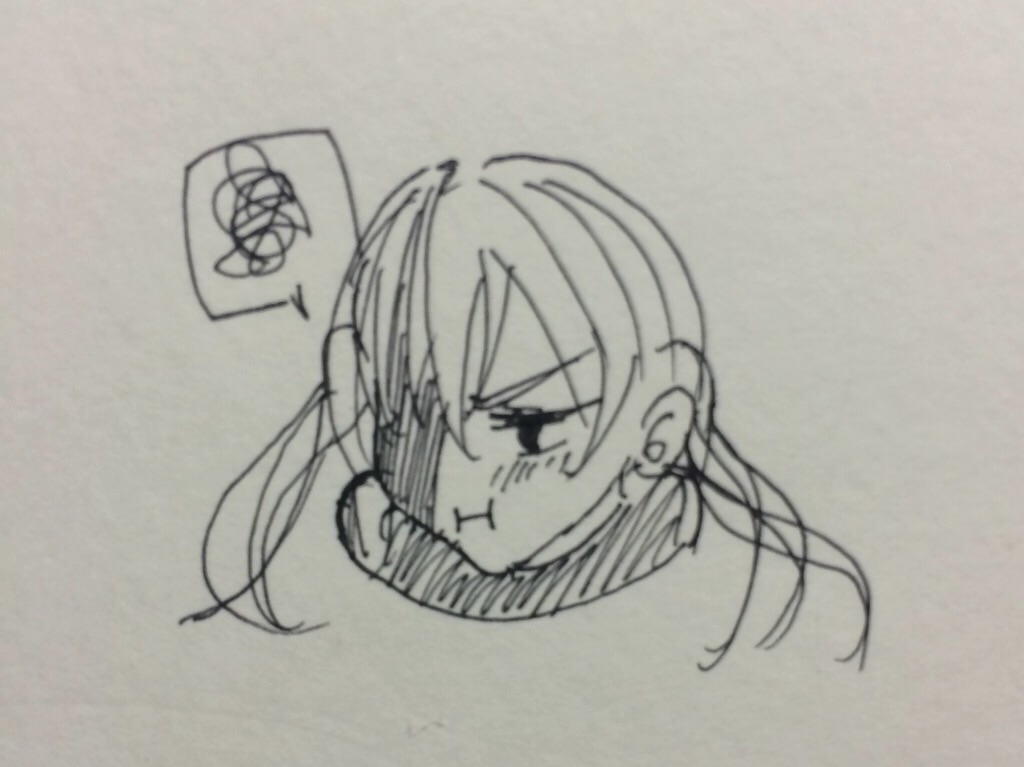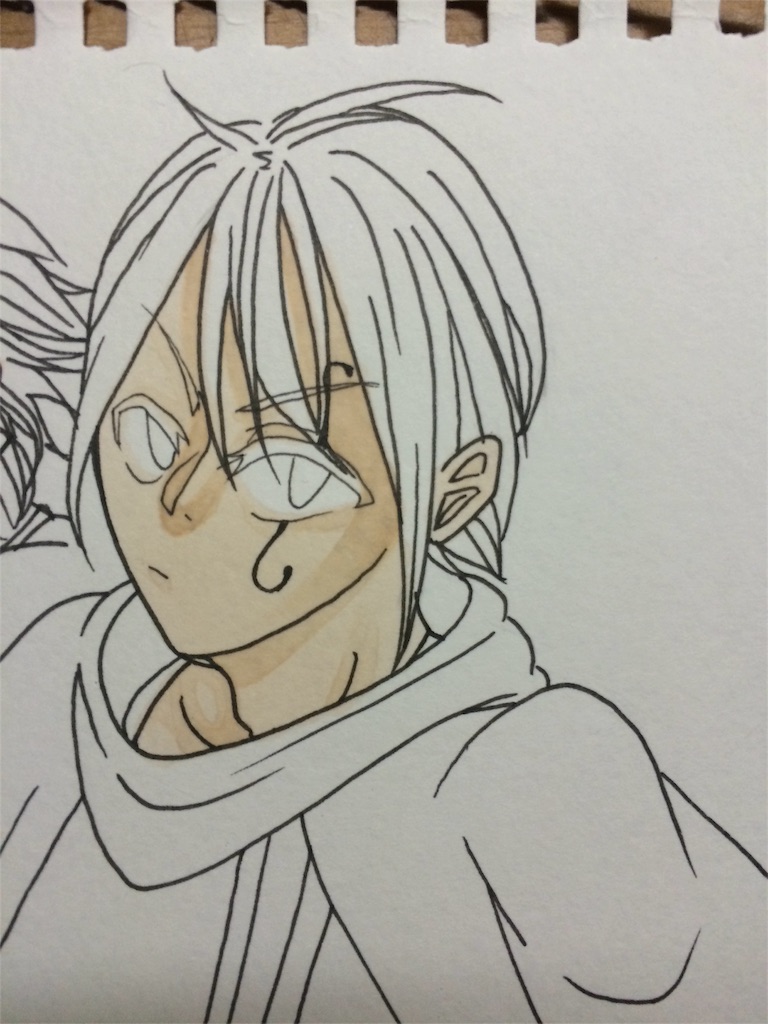寒い冬の日のことであった。
窓の隙間から冷たい風が入りこみ、白く曇っている窓の外には、静かに雪が降り積もるそんな日であった。
12月17日、俺は人間の父と天使の母から、天界最強の戦闘部族、テラス家の長男として産まれた。
その2年後、9月28日には妹が産まれた。
俺は人間の血を半分以上受け継いだもの、妹は体の弱い母の血を色濃く受け継ぎ人間の血はほんの少ししかないという。
俺は人間の父より、妹は天使の母よりに、妹は体が弱いけれど俺達は元気に幸せに育った。
そんな俺達は両親の昔は凄腕の武人だった、という話が大好きであった。
父は下界で最強の剣士と謳われ、母の弓の腕の凄さといったらこの世界中で右に出るものはいないという話だ。
そんな両親に俺は憧れを抱いた。
俺は両親に1年間必死こいて武術を教えてくれと毎日頼んだ成果により、母から天界最強の戦闘部族と言われた『雷天族』の武術をみっちり叩き込まれた。ちなみに雷天族とは、大昔人間が雷を自在に操る天使を見たから、というなんともそのまんまな名前である。
だが話のとおり、俺達は雷を自らの魔力で発動することができるのだが。
そしておかげで、戦闘学習必修の天界最大の学院を特待生で入学できた。
なんて充実した幸せな生活だろうと、その時俺は思っていた。
だけれど俺は後悔する、武術を学んだことを、この家に産まれたことを、妹を恨んで、羨ましいと思ったことを、この先後悔する。
それはとりとめのないごく普通の日であったその日、人生を360度変える出来事が起こった。
俺はこの日味わった思い、光景を2度と忘れないだろう。まるでフィルムに焼きついた写真のように脳裏に張り付いて消えてはくれない、地獄の日を。
これは『俺達』の醜い残酷な、悲しい復讐劇。
革の表紙と無地の紙で作られた本を開く。
インクが入った小さな壺の蓋を開けて、羽ペンをインク壺に突っ込んで本にペンを走らせる。
1時限目は魔法学。俺が数ある授業の中でもっとも好きな授業だ。
「1時限目から魔法学かよ〜、インセットインク借りるわ〜」
おもむろに話しかけてくる隣の奴がペンをインク壺に入れる前に、インク壺の場所を素早く移動させる。
ペン先は行き場なく、机にぐさりと刺さった。
「自分のインクを使ったらどうだレイト」
「暇なんだよ魔法学……」
レイトはまだ始まって5分程なのに集中が切れたようだ、しかも手元のノートには3行くらいで終わっており黒板の量にはほど遠い。
「……また寝坊したんだろ」
「正解」
「お前もう学院の宿舎借りたほうが成績の為だぞ」
「じゃあお前も学院に泊まろ?借りよ?お前家遠いじゃ〜ん」
「馬鹿っ引っ付いてくんな鬱陶しいわ!」
そんなこんなふざけて、まぁ一方的なおふざけをしていると先生から注意をうけ、生徒から視線を感じたので俺は直ぐに静かにした。
俺は学院1000人以上の中で戦闘5位、勉学3位の順位をもつ、周りからは「優秀」という部類に入るらしい俺はそれなりに有名らしく、男子からはよく喧嘩を売られ、女子からはよくラブレターだの手作りお菓子だのを貰う。
だが、そのように毎日を過ごしていたら静かに勉強出来ない。俺はここで学ぶことが楽しみでしょうがないのにとても困る。さらに、周りに迷惑をかけてしまうだろう。
さらにもう一つ、学院中の女子に物申したい。
俺はお前らに興味はない、俺の妹の方が何万倍も可愛いわ。
お前らよりもキラキラ輝く綺麗な目とお前らより綺麗でサラサラな銀髪に白髪が混ざった美しい髪、全てが可愛い頭から足の先まで可愛い。
お前らとは何もかも違う可愛いさだ、だからお前ら学院内の女子に微塵の興味もないわ!!
なんて、ニヤニヤしているのをレイトは冷ややかな目で見ているのは触れないでおこう。
「あ、そういえばインセット。今度一緒に俺ん家で遊ぼうぜ」
「それは今、この授業中に言うことかレイト?」
「だって休み時間まで覚えてられないだろ?思いついた事はすぐ言わないと」
「別にいいが……お前ん家で何すんだよ」
俺は板書の要点だけをノートにまとめながら横目でレイトを見やる。
レイトは天界ではきっと最も有名な一族であろう。
何故なら天界の『王族三家』と言われるからである。
そして天界は『王族三家』と呼ばれる王族から、現王が退位した場合その年内の間に3つの王族が協力して選挙が開かれ、民はその3つの王族から君主を選ぶ、ということだ。
そして当たり前だが、天界で権力を握っているのは神であるため、王族は神である。
王族三家は、ウル家、
ライラック家、シャレーヌ家だ、レイトはその中でもっとも王を輩出する王族のウル家の3人兄妹の次男である、ちなみに現王はレイトの実の父であり、この人がまた凄い方なのだ、歴史上最も最悪の大戦と言われた人間との戦、この世界は軽く4億年は存在しているがそのうちの三千年間戦い続けた戦に終止符を打ち、大戦で疲れ果てたこの世の再建を行い以前より良い世界へとさせたのだ。
俺はそんな身分の違いすぎる家で何をして遊ぶのか全く思いつきやしない。
「そうだなぁ…今度の土曜日に俺ん家で姉さんの誕生日パーティーをするんだ。どうだ一緒に」
「……パーティーか」
「家族だけで毎回やってるんだが、たまにはな?それに何故か父さんがお前を気になってて」
「レイト、良かったらなんだが」
俺は1通りノートに写したのでペンをおき、レイトの方を向く。
「妹を一緒に連れてやってもいいか?」
「もちろんだ!人数は多い方が面白いしな!それよりお前、妹いたのか」
「あぁ体が弱くて、滅多に外に出ないんだがここのところ良くなってきてな、街を見せてやりたいついでなんだが……」
「そうなのか、そりゃ立派な思い出にしてやらないとな!ゆっくり回ってから来いよ、あぁそれなら俺の城下に凄い飴屋があるんだ、そこオススメだぜ」
「そうか、そうだな。喜んでくれるかな」
「当たり前だ、なんせ始めて街を見るんだろう?そりゃ驚くさ」
「あぁ、じゃあよ。今日終わったらどこ回るか決めるの手伝ってくれよ」
「面白そうだな、いいぜ!」
それから15分は立ち、授業も終盤になったところだ。
すると、教室の扉が大きな音を立てて開かれた。
教諭札を胸元につけているので先生であろう男が息を切らせている。
きっと教室がある校舎から職員室がある校舎をおよそ2km走って来たのだろう、お疲れ様、そう他人事に思っていた。
だがなんだか嫌な予感がした。
「インセットっ!!インセット=テラスはいるか!」
「え、あぁ?…はい!インセットですが!」
予想は的中、はて俺は何かやらかしただろうか。
ここにいるとアピールするために椅子から立ち上がり手を挙げる。
すると教師は疲れているのか階段を上がってはこなく、扉のところから大声で俺に話しかけた。
だがその話はあまりに唐突すぎた。
ここから俺の人生は360度変わることになるとはまだ思いもせずに。
「お前の家がある天界最南端の森が現在人間が進行中!さらに交戦予想の区域にあり、大規模集団が向かっているとのこと!このままでは戦火に飲まれる危険性があるので生徒の身の危険を考え、今日は帰宅を禁ずる!現在その地域に住む生徒にも緊急で連絡しているので安心しろ」
俺は立ち上がったまま棒立ち状態になってしまった。
いきなり何を言っているんだこいつは。
人間?交戦?戦火?安心しろ?
俺はいきなり過ぎる情報をゆっくりと頭で整理してから落ち着いて、言葉を選んで口を開く。
「……それ…は……家族を見捨てろと…?」
「しょうがないことなのだ、交戦は長期の予想だ。一週間はかかると上が…」
教師はこめかみを押してこちらのことなど考えもせず、溜息をつく。
周りがさきほどの静寂を押し倒し、ざわめき始める。
「俺もその森に近いんだが…」「どうなるの…?」などと周りからの不安の声に、歯を食いしばる、歯が割れるんじゃないかというほどに力をこめる。
母も父も元軍人だ、父は人間だが最強と言われていたらしい、母も有名な軍人だという。
だが。
「………アモル…アモルは………?」
俺は無意識に妹の名前を口にする。
まるで暗闇の中でそれを手探りで探すように。
妹は体が弱くて、毎日ベッドから窓の外を見ていた。
持病もあり外に出たことのない妹にいつも帰ってから今日の話を聞かせるのだ。
妹は輝く目で俺の話から、外について毎日毎日考えていた。
なのに、それなのに。
「行ってこい、インセット」
「え……」
レイトに背中を思いっきり押される。
俺は反射的に後ろを向こうとするとレイトにとめられる。
「あぁいい、いい。後ろは向くな、これは貸しだぞ」
「お前に貸しとか最悪だな」
俺は少しだけ口元を見せるようにレイトにニヤリと笑ってみせ、俺は机に手をつき、足を振りあげて階段状の机、3mをひらりと飛び越えると、周りから悲鳴にも似た声が湧き上がる。
すると、先程の教師が両手を広げて俺の前に立ちはだかった。
「インセット!止まるんだ」
無表情で教師は俺は俺に警戒しながら近づいて、乱暴に腕を掴まれる。
「いいか、お前は優秀だ、可能性がたくさんあるんだ。これからお前は何だってなれる。己は大切なものだと理解し」
「反吐がでるわ」
俺は腕を振り払い、躊躇いもなく教師の顔を力をこめて殴った。
おかげで教師の言葉は最後まで発せられることなく体は後ろに吹っ飛んだ。
息をこれでもかと吸い込み、そして吐き出す。
「俺の大切なものは強さでも才能でも可能性でもなんでもねぇ!!家族が一番大切なんだよ!!」
俺は教師に吐き捨てるようにありったけ叫ぶ。
そうして大理石で作られた廊下を思いっきり蹴った。
教師は肩膝を地面をつけ、声を張り上げた。
「インセット待ちなさい!」
「すまんな先生。インセットに貸し作んの、なかなか難しいんだよ」
人差し指に凝縮させた赤い玉を先生の首元に突きつけニコリとレイトは笑った。
俺はそれを横目で確認し走り出す。
「母さん……父さん……アモル……大丈夫…きっと大丈夫…!」
俺は学院の玄関の扉を蹴っ飛ばす。
転がるようにして立ち上がり、校庭をつっきる、まれにすれ違い様に俺の名前を言われたり、ぶつかったりして謝ったりを繰り返して正門を飛び出る。
「こら!!君まだ授業の途中ではないのか!」
正門の警備員に腕を捕まれるが振りほどいて走り出す。
学院前の坂道を勢いつけ走り、レンガの地面がありったけ踏みつけ飛び上がる、肩甲骨を真ん中に寄せるように動かして、羽根をまき散らしながら翼をだす。
翼で飛ぶのは地を走るより圧倒的に速く移動できるが長時間の飛行は体力を削る。
だが今はそんなことは気にしていられない。
俺が通う学院は天界の政府ーー天界は王政なので王様が統制しているのだが、政府が直に運営する学院なので情報が軍の次に早く入ってくる。
だから民間にはかなりの時間差で情報が伝わるので、家族はきっとこの情報を知らない。
俺が知らせて、みんなで逃げないと。
妹は、家族は俺が守るんだ…!
背中の筋肉が悲鳴を上げ始めたころ、視界には見慣れた森が炎をあげて待っていた。
森入口周辺には野次馬たちがうじゃうじゃと集まりまるで蟻のようである。
「そんな馬鹿な……」
俺はショックやら疲れやらで頭がごちゃ混ぜになり、半ば強制的に翼をしまう。
おかげで建物の屋根に激突し、そのまま2m程落下し地面に強打。
俺は痛みに身悶えていると、人々が俺によってきて俺を真ん中にサークルが出来てしまった。
その中には数人顔見知りがいて、八百屋のおじさんが俺に話しかけてきた。
「お前、森んとこのガキじゃねぇか!なんだ無事で良かったなぁ!」
「っ………無事に、見えるかっ……、どう見ても痛そうだろっ…!!」
「はははっ生きてて良かったという意味だ、なんせお前んとこはうちの大事な客なんでなぁ」
「そりゃどうもっ…!」
地面に両手をつき、体をめいいっぱいの力で持ち上げる。
こんなところで油売ってる場合じゃない。
「おい!どこ行くんだ!」
俺は力を振り絞り地面を思いっきり蹴った、周りの人たちの頭上をひらりと乗り越えバランスを崩しかけたもの着地して、燃え盛る森に飛び込んだ。
熱気と盛んに飛ぶ火の粉に気圧される。
だが入ってしまえば近道を通って片道2分で着く、大丈夫、俺なら行ける、そう自己暗示をかけて走り出す。
燃える曲がりくねった道をものの数分で通り抜けると、まだ燃えてない見慣れたログハウスが待っていた。
俺は叫びたかったけれど体力の激しい消耗と息苦しいさ、熱気、そして諦めで声は出なかった。
俺はヨロヨロと階段を数段上り、木でできた手作りのドアノブにゆっくり手をかける。
きぃ、と音をたて開かれた扉の奥、リビングには2つの影。
俺はチラチラと燃える床を踏みしめた、怖くて近づけない、だけど俺は確認しなければ。
俺は母の体の側に静かに座り、母の顔に震える手を伸ばす。
「ごめんね……インセット…」
「母さんっ!」
俺は母が生きていたという事実に涙が零れた、けれど本当はわかっていたのだ。
「インセット……幸せになるのよ…?お母さんもう…貴方に触れられないけど……」
「何言ってんだよ母さん!俺はっ俺…」
母は涙をいっぱい溜めて、いつものように優しい温かいで俺の頬を撫でると、涙を愛おしいものをめでるようにふく。
「アモルは外に逃がしたわ…早く、見つけて……」
「え……?」
「貴方達を……深く、愛しています…アモル、インセット……私達の…大切な……たか、ら…もの……」
最後に額にキスをすると、何かが切れたように手は滑り、床に力なく落ちた。
「……か、母さん…母さん、母さん……母さん……かあ…」
しばらくはただ静かに泣いていた、周りはだんだんと熱くなってきて息も苦しかった。
でも動けないのだ、だって母がまだ腕の中に。
だが背後から音がした、俺は視線だけを移すがまさかそこにいたのはクラスメイトであった。
「レイト……」
「早く外でるぞインセット!!俺の力じゃ手に負えない!」
「……母さんが」
「そんなこと言ってる場合かよ!いつもの生意気なお前はどこいったんだ!?」
「黙れ!!お前にはわからないだろ!お前はこの世で一番偉い神様で!産まれた時から地位と才能があってよ!!だからわからないだろう!?俺は天使、普通の天使だ!産まれた時からあったのは小さいけど充分な幸せだ!でも、それだけだったんだよ!!それだけが……俺の生きる意味だったのにっ……!それだけあれば良かったのに!!!」
俺はレイトのマフラーを母の血で濡れた手で乱暴に掴み、引き寄せる。
「俺は何のために、何のために今まで頑張ってきたのか……もう、わからないんだよ。お前にはわからないだろうな。この、小さな幸せが、どれだけ温かくて、嬉しくて……わからないだろ……っ!」
「イ、インセット。その、俺、は……別に」
「教えてくれよ神様、俺の生きる意味を」
涙は拭かなかった、今は睨みつけるので、理性を保つのことに必死だった。
だが、レイトは俯いたままで悔しそうに唇を噛んでいた。
その後、身寄りがない俺はレイトの家に暮らすことになった。
「大昔だ、君の母は大戦時代、親友であり、戦友であり、そして大切な相棒だった。戦争が終わった後は静かに暮らして欲しかったから連絡はしていなかった。これは俺の責任でもある、本当に申し訳なかった」
と、頭を下げられてしまったが。
そして家族の死から数ヶ月たち、夏の到来を感じる時期になった。
母は死ぬ前、妹は外に逃げたという。
だが探しても探しても見つからない。
俺にはもう、生きる意味がなかった。
「インセット、おはよ。今日も弓の鍛錬か?」
夏でも白いマフラーをしているレイトが笑顔で向こうから近寄ってきた。
俺は立ち止まってレイトの顔を真っ直ぐみる。
「あぁ、そうだが」
「たまには俺もやってみようかな〜!…なんちって!」
「いいんじゃないか」
「なぁインセット、今日の昼街に出掛けないか?」
「すまん、昼は体術の練習だ」
「じゃあ!今日夕飯食い終わったら…」
「すまんな、夜は出掛けるんだ。
ウラノスさんに言っておいてくれ」
「じゃ、じゃあさ!明日の朝一緒に」
俺はレイトの隣を何事もなかったように通り過ぎる。
背後からは悔しいそうな声が漏れてるのが聞こえたが、俺は何も感じなかった。
的から20m離れた地点にインセットは弓と矢を持ちたっているのを窓から眺める。
ここ数ヶ月、インセットは落ち着いてきている。
前は部屋に篭って飯に口をつけないほど落ち込んでいたが、大分俺の家族にも慣れている。
その点は安心だ。
だが、俺とインセットの距離が日に日に離れていく気がするのだ。
インセットは笑わなくなった、たまに見せる笑顔は作り笑いで、目に隈もできている。
しかも最近はよく弓や体術、刀、槍、とにかくいろいろな武術やらを猛練習している。
インセットがインセットでなくなっていく。
まるでからくり人形みたいに、毎日毎日同じことをキチンとこなし、それを繰り返している。
会話は「そうか」「すまん」「そうだな」とか一言、一文で終わることが多い。
このままではインセットの心が死んでしまう。
どうにかしなければと行動してると。
それは事件から一年たったある日、驚きの知らせが届いた。
「君の妹が見つかった、名前はアモル、だね」
「…………それ、は」
「わかる、なんせ事件から一年だ。信じられないのも無理はない」
「…………はい」
インセットは一瞬驚きの表情をみせたもの、直ぐに無表情で冷たい顔に、目は黒く曇ってしまった。
隣で一緒にその話を聞かせれている身としては、インセットの心がまったく見えない。
「父さま、インセットの妹は何処に?」
「実は居場所を特定できただけなんだ」
机の資料を魔導投影器の上にのせると、空中に音を立てて資料拡大した物が現れる。
「ここ最近立て続けに天使の子供が攫われていた、だがある時期を堺にハタリと止まる、それがお前の妹が消えた時だ、まるで、その〜、探し物が見つかったみたいな…」
「妹が探し物だと言うのですか」
「あぁ、犯人が攫った子供の家は不規則なんだ、同じ場所だったり、はたまた何キロも離れてたり」
俺はその事実よりもインセットが反応したということに驚いただけだったのだが。
「それで、妹が消えて半日たらずで下界で子供の大集団が森で発見」
映し出された資料が写真に移り変わる。
「そしてその付近、というか手当たり次第探した、この一年な。そしたら怪しい研究所が、もう怪しいっていう希望なんだけど、やってみるしかないんだが」
「この建物に奇襲をかける」
風のない雪の中、ついにこの日がきた。
上手くいけば一年ぶりの再会である。
下界北部の寒帯の針葉樹の森の中、一本のドッシリした古い大木の枝にレイトと共に座る。
大木の枝は人が枝に対して垂直の向き、つまり縦に寝ても余裕があるほど一本一本の枝が大きいのだ。
天界にあるこれほどの木にはだいたい妖精の住処になっている、彼らは縄張り意識が高いから少し不安だがあいにくここは下界、滅多にない機会に少しワクワクした。
しかしそんな俺とは反対に、先程から隣でブツブツと聞こえる声にそろそろうんざりしてきた。
「もう、うだうだ言うなよ……」
「最悪だ、俺マフラーできねぇのかよ」
「奇襲に白は最悪だしな」
「だけどマフラーないと俺が誰だかわからないじゃないか」
「わかるから大丈夫だって」
「でも俺マフラーないと安心しないというか」
「レイト、わかったからもう静かにしてくれよ…」
木の太い枝に立ち、黒いロングコートに身を包んでいたがさらにフードを深く被る。
相棒である
コンパウンドボウと呼ばれる弓を左手で握り、右手で矢を背中の矢筒から一本取り出して、ノッキングポイントにセットする。
周りから雑音を排除するために目を瞑る。
雑音……クリア。
俺は標的をロックする。
標的は侵入経路であるドア10個の内3つの鍵を全て爆破すること。
南に2つ、120m離れた南東に1つ、ここからの距離はおよそ700m、残り時間2分と15秒で突入。
俺は弓を真っ直ぐ持ち上げ、肘と矢が一直線になるようにし今できる最大の力で弦をひく。
この矢は特注品で的に当ると起爆装置が起動し、三秒足らずで魔法陣が形成され爆発するので失敗はできない。
ありったけ10秒溜めて弦を離す、矢は俺の予想通りに飛んでいき、5秒後にはドアに音を立ててあたる。
「ビンゴ」
爆破音が聞こえ、俺は直ぐに矢をセットして今度はテンポよく一本、二本と全てをスムーズに終わらせる。
魔導式インカムを起動する、耳中心から円を描くように魔法陣が現れ常に回っていることを確認し、弓を背中にしまい代わりに短剣をだす。
「こちらインセット、3つの侵入経路確保を確認。ステップ2に移行します」
『こちら突入部隊、いつでもいけます。
ウラノス様の指示を待機中…………突入許可が降りました、そちらが突入したら我々も』
「あ〜、レイト準備完了、今から派手に突入していいですか父さま」
「おいおいレイト……奇襲だっつってんだろ」
「大丈夫大丈夫、というかお前も奇襲何かより一年間分の怒りを暴れて解消したくないか?」
やりたいもんならやってやりたいが、この作戦に参加するにあたって条件がある。
人間であろうが天使だろうが妹関係なく必ず助けることだ。
条件には反しないが、それは誘拐された子供に危険がかかる可能性が…。
『レイト、派手に突入していいぞ』
「マジで父さま!」
2人の声が重なり顔を見合わせる。
インカムの向こうから笑い声が聞こえた。
『インセット』
『ブチかましてやれ』
レイトがニヤリと不敵に笑う。
レイトは手を右手を腰に、左手に炎を出して早くしろ、と目が輝いてる。
きっと
ウラノス様も若い頃はこんなんだったんだろうと、安易に想像できる。
親子揃って戦闘大好きという事実に苦笑いしかないが、ここは素直に頷こう。
「本当にいいんですね?」
『あぁ、帰ったらみんなでパーティーだ』
俺は短剣をしまい、暴れる用というか本業の体術で挑むとしよう。ズボンのポケットから黒革の手袋を取り出す。
手袋には俺の魔力分子を布の繊維に組み込むことで、俺が雷を発動しようとすると手袋の魔力が反応して手から雷が出すことができる。
「準備はいいか?相棒」
「相棒って俺に言ってんのかよ」
「俺が炎でドアをぶっ飛ばす、そのあとはまかせた」
俺は木の枝を蹴り、雪の降り積もった地面を前転して立ち上がる。
「さて、天界を敵に回したことを後悔させてやる」
「そのいきだインセット」
小走りで俺達はドアに駆け寄る、レイトに手で合図を送り、それを確認したレイトはまるで空気を撫でるようにドアの前で手をスライドさせる。
するとドアからチラチラと炎が現れたと思うとカタカタ音をたてたのち、爆発した。
俗に言う発火能力『
パイロキネシス』みたいなものと理解してくれた方がいいだろう。
それも説明するとまったく違うものだが、レイトは炎を操ることに関して右に出る者はいない、そしてレイトの兄は空間を操る天才、姉は剣の天才、まったくコイツん家には天才しかいないのだろうか。
するといきなりドアの上のランプが赤く変色し、警報音が喚きはじめた。
『侵入者、侵入者、総員直ちに排除せよ』
『レベル6の被験者は部屋から出ないように』
と、同じ放送を何度も繰り返していた。
「……レベル6って何だ?」
「それも調べるか、行くぞレイト」
走って中に突入する。
上の方はもう銃撃戦に入っているのか騒々しい。
「インセット!右!右右!」
俺は右に視線を向ける前にかがんで地面に両手をつける、そのまま足を回転させて敵と思われる奴の足元を蹴る。
倒れた敵にまたがって、相手が何かを言う前に顔面に一発殴り込み気絶させた。
「その〜……お前って案外、凄いな」
「そりゃどうも」
「おいインセット、そっちにもう子供はいないか?」
「あぁいない、天使しかいないぞ。ここの研究所は一体なにを……」
「おいインセット」
レイトに肩を叩かれ後ろを向くと、『レベル6』と書かれたドアがあった。
「レベル6……」
「どうする」
「いくしかないだろ」
俺はレイトを後ろにドアノブに手をかける。
中からは音一つ聞こえない、警戒しながらもゆっくりと扉を開いた。
中はただ巨大なだけの白い部屋だった。
何もない白い部屋だったが、部屋の一番奥の右隅に黒い人影があった。
「あそこに子供たちがいる、行くぞレイト」
駆け足で子供たちに近づく、人数は4人、翼を出していないのでまだ天使かは断定出来ない。
怯える子供たちを安心させるために、片膝を地面につけて視線の高さを合わせてからなるべく笑顔で話す。
「初めまして、俺はインセット、こいつはレイト。君達を助けに来た」
「あなた………アモルのお兄さんね…?」
真ん中にいた両目を包帯で隠した女の子が立ち上がった。
まさか妹の名前が出てくるとは思わず不意をつかれた。
「アモルはここにいるのか」
「えぇ。私達はレベル6よ、ここの研究所にはレベル1から6までに子供たちを分けて何か研究してるの」
「なんでこんなところに?」
「死神が、強くしてあげると言ってきたの。ここの子は病気だったり能力が抑えられなかったりする子が多いから…」
「君達は?」
「死神は、
七つの大罪と呼んでいるわ。私達罪なんて犯してないのよ?それに本当は20人数以上いたの」
「何処に行ったんだ?」
「死神に連れてかれてから誰も戻ってこないの、アモルもさっき連れてかれたわ……」
「…連れてかれた子はどうなるんだ」
女の子は一瞬口を噤んだが、右の壁を指さして震える声でいった。
「死神に殺されるの」
たっぷり10秒の沈黙が流れる。
俺は沈黙を壊すように、音をたてて走り出す。
先程指さされた場所に向かって飛び蹴りをかますと、白い壁は壊れ、白い道が現れた。
「お………けて……だ…か」
道の先から途切れ途切れに聞こえてくる声は確かに妹のものだ。
幸い道は長くなさそうだ、俺は妹に会える嬉しさと不安で自然と足が速くなる。
道が開けた先には妹がいる、俺は大きく足を踏み込んだ。
「アモルっ…………?」
「……おにぃちゃん……」
妹は目に涙をいっぱい溜めて今にも溢れそうである。
だが、だがそんなことより俺は。
「……何だよ、これ…」
妹は山と積まれた無数の死体に囲まれていた。ここは死体廃棄か?とも思ったが一瞬、思ってはいけないことが脳裏をかすめる。
妹にゆっくりと目を向ける、白いロングワンピースの裾はボロボロに破けている、傷もない、だが唯一不信な所と言えば、全身血だらけ、いや外傷はないので出血ではない、だとすると返り血である。
妹は何をしたのか、ここで何をされのか。
「…私、私じゃ、ないの……私た、助け、たくて……」
「あぁ…あぁ、大丈夫、お兄ちゃんが助けにきたから、もう大丈夫だよ」
俺は血だらけの妹を腕に抱き上げる、背中を優しく叩きながらまるで赤子があやすように。
「帰ろうアモル……」
「…うん、ごめんなさいおにぃちゃん、ごめんなさい私……お母さん…逃げたの、怖くて」
「もういいんだ、お兄ちゃんはアモルが居ればもういいんだよ……」
俺は妹に死体の山を見せぬよう顔を俺の肩につけるように押さえて後ろをむく。
どうやら、これはただの誘拐事件で済む話ではなさそうだ。
俺は妹を抱き上げながら、インカムを作動させる。
「
ウラノス様、妹発見しました、外傷は見られず意識もしっかりしています」
『それは良かった!じゃああとは俺の部隊に任せてレイトと一緒に帰還して構わない』
「いいのですか?まだ子供たちを全員保護していないのでは?」
『妹片手に仕事は出来ない、だろ?』
「ははは、お見通しですか」
『お前の笑い声は初めて聞く、本当に良かったなインセット』
「……えぇ、ですが帰ってから報告したいことがあります、この事件ただの誘拐事件ではなさそうです」
『……何故そう思う』
「死神がどうやら関係しているかと」
『…死神か……ここ数百年は聞かぬ名だったのだがな』
「帰ってから話しましょう、その方が落ち着きます。なんせ一年ぶりの再開ですので」
『そうだった、引き止めて悪かったなインセット』
音声は向こう側から切れた、俺はインカムをオフにする。
「おにぃちゃん…誰とお話してたの……?」
「そうだなぁ…俺達を守ってくれる強い人だ」
「お母さんとお父さんには……もう会えないの……?」
俺はどうしようもない事実に何と答えていいか戸惑う、だがここでうやむやにしてはいけない。
アモルの頭を優しく撫でながらゆっくり話す。
「……アモル、お母さんとお父さんには……もう…会えない………でもな、それはアモルのせいじゃないよ、お母さん最後に言ってたんだ、俺達を愛してるって。お父さんもきっとそうだってお母さんが言ってた」
「あいしてる……?」
「俺達が大好きってことだよ」
「アモルも、お母さんとお父さん大好き!お母さんは優しくてあったかいの!お父さんの手は大きくてねカッコイイ!それにおにぃちゃんも大好き!」
「ありがとうアモル、アモルは優しいなぁ」
「えへへっ……でも……でもね、アモルも……おにぃちゃんがいれば大丈夫だよっ、だっておにぃちゃんも悲しいのに我慢してるから……アモルも我慢するっ!1人じゃないからアモル我慢できるよ!」
「アモル……ありがとう、いい子だなぁ流石俺の妹だなぁ」
妹は目に涙をいっぱい溜めて笑顔でジタバタと足をふる。
元の広い白い部屋に戻ると、子供たちは避難したようでレイトがど真ん中であくびをしてまっていた。
「遅いぞインセットっ!おっそれが噂の妹か」
「すまんなレイト、ちなみに俺の妹に気安く近づくな」
俺はレイトが歩み寄ってくるのを片手で止める、なぜなら妹が怖がっているからだ。きっとそうだ。
「あなた、だれぇ……?」
「俺はレイト=ウル、君のお兄さんの友達だ。君を助けに来たんだ、なんせお兄さん、君を毎日探すもんだから」
「おにぃちゃん、ほんと?」
「……まぁ、うん、そうだな…」
レイトの方から「何照れてんだよ」と視線がおくられてくるのを、あくまでも笑顔で、そして声は優しく「お前、後で覚えてろよ」と伝える。
事件は解決した。
攫われた子供たちは全て天使であり、健康状態を確認してから親の元へ送り届けられた。
犯人は不明、施設も用途不明、子供たちも一体何の為に集められたのかもわからない。
でもわかったこともある。
『死神』『
七つの大罪』について調べる必要がでてきた。
そして妹の件について。
妹は何故血だらけであったのか、何故両親は殺されたのか。
全て、知らなくてはならない気がするのだ。
〜死界〜
「ひー、ふー、み〜、と〜……あっちゃー!アイツらぜぇ〜んぶ持っていきやがった!」
「まぁいっか、どうせそろそろ返すつもりだったし」
「一回目は何ともつまらなかったからねぇ、あぁでもアイツを殺してやったときの顔は覚えてる覚えてる」
黒い前髪を書き上げ、けたけたと暗闇の中で笑う。
金色の目を楽しそうに輝かせながら、黒いドブに腰を降ろして足をジタバタさせている。
「アイツの顔、アモルの顔はまさにびっくり〜って感じだったなぁ、はははははっぁは!!」
「腸引っこ抜いてさぁ〜!ぶふっ、その後目の前で両手両足斬って、斬って、斬って斬ってさぁ〜」
「最っ高だったなぁ、あぁいかにも」
「怒りに満ちた顔だった、俺を殺したくてたまらない顔だった、そうそう、そうだった」
「アモル=テラスだ、そうだったぁ!!」
押さきれぬ笑みを手で覆って、暗闇の中でけたけたと笑い続ける男は、はて、何者か。
ある者は「疫病神」と。
ある者は「ただの馬鹿」だともいった。
彼はこの世界を創造した2人の内1人、この世の闇自身である。
彼はこの世全ての悪を背負う者、「アンリマユ」と呼ばれる。
またの名をーーー『死神』。
この物語は、どうしようもなく世界が創造された時から始まり。
彼のどうしようもない、ただの暇つぶしである。